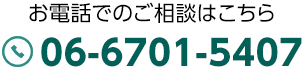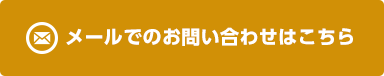2025年1月~12月
令和7年度 税制改正のご案内(2025.11月号)
●令和7年度 税制改正のご案内(2025.11月号)
令和7年12月の年末調整より、「賃上げと投資による成長型経済」への移行を後押しするため、税制改正が行われます。
今回の改正の背景には、物価の上昇による税負担の増加や、最低賃金の上昇によって「扶養の範囲内で働く時間を抑える人」が増えている問題があります。今年の年末調整から影響が及びますので、以下、給与で働いている方やそのご家族に関係する主な改正点を解説します。
---
1. 基礎控除額の引き上げ
基礎控除とは、所得税を計算する際に収入から差し引ける金額のことです。
今回の改正では、合計所得金額が2350万円以下の人について、基礎控除が一律10万円引き上げられます。
さらに令和9年までの2年間は、所得の金額に応じて次の通り加算されます。
(※ 所得金額は「年収」から給与所得控除などを差し引いた金額です。)
所得132万円以下:加算額37万円(年収の目安 約200万円以下)
所得132万円超から336万円以下:加算額30万円(年収の目安 約200万超~約475万円以下)
所得336万円超から489万円以下:加算額10万円(年収の目安 約475万超~約665万円5千円以下)
所得489万円超から655万円以下:加算額5万円(年収の目安 約665万5千円以上~850万円以下)
---
2. 給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得控除とは、会社員など給与で働く人に認められる「必要経費のような控除」です。
改正前は、年収162万5000円以下の場合の控除額は55万円でしたが、今回から65万円に引き上げられました。
これにより、特に年収190万円以下の方にとって有利になります。
以下、改正後の給与所得控除額の目安です。
・年収162万5000円以下:65万円(固定)→今回改正
・年収162万5001円から190万円以下:65万円(固定)→今回改正
・年収190万円超から360万円以下:収入金額×30%+8万円 →従来通り
・年収360万円超から660万円以下:収入金額×20%+44万円 →従来通り
・年収660万円超から850万円以下:収入金額×10%+110万円 →従来通り
・年収850万円超:195万円(上限)→従来通り
※年収190万円を超える方の計算方法は変更ありません。
---
3. 特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の子どもなどが対象となる新しい控除が設けられました。
この制度では、対象となる家族の合計所得が58万円超から123万円以下(給与収入で約123万~188万円)である場合、控除を受けることができます。
給与収入が150万円以下であれば、控除額は最大63万円です。
給与収入が150万円を超えると、188万円までは段階的に控除額が減っていきます。
---
4. 扶養親族および配偶者の所得要件の見直し
これまで、扶養の対象となるには「合計所得48万円以下(給与収入103万円以下)」である必要がありましたが、今回の改正で「所得58万円以下(給与収入123万円以下)」に引き上げられました。
そのため、年収123万円までであれば、扶養親族や配偶者控除の対象となる可能性があります。
---
■ 今回の改正による主な影響
● 本人及び配偶者の、いわゆる「103万円の壁」が「160万円の壁」に
改正により、次の控除を受けられる場合、令和7年および8年に関しては年収が160万円までであれば所得税がかかりません。
・基礎控除:48万円+10万円(今回引き上げ分)+37万円(R7.8限定特別加算分)=合計95万円
・給与所得控除:55万円+10万円(今回引き上げ分)=合計65万円
95万円+65万円=160万円となるため、所得がゼロとみなされ、所得税がかかりません(これは年収が200万円までの方のケースで、年収が上がるにつれ特別加算分が逓減するため、壁の金額は変わります)。
令和9年度以後は改正が無ければ、
・基礎控除:58万円
・給与所得控除:65万円
58万円+65万円=123万円で、「160万円の壁が123万円」となります。
また本人の収入だけでなく、配偶者の年収も160万円までなら、源泉控除対象配偶者としてカウントできます。
---
● 扶養親族の「103万円の壁」が「123万円の壁」に
扶養に入れるための基準が「年収103万円」から「123万円」に緩和されました。
これは、給与所得控除が65万円、扶養の所得条件が58万円に変わったためです。
但し源泉控除対象配偶者は、年収160万円まで扶養親族としてカウントできます。
---
■ 実務上の注意点
年末調整などで注意が必要なのは、「特定親族特別控除(19歳から22歳のお子さんの収入)」です。
お子さんの収入がいくらになるかを正確に確認し、申告書に記載してもらう必要があります。
ただし、昨年の定額減税と比べると、手続きの手間は少ないと感じられる方が多いかもしれません。
---
■ 最後に(社会保険の扶養について)
今回の改正はあくまで「税金」の見直しです。
「社会保険の扶養(年収130万円、60歳以上は180万円)」については変更ありません。但し19歳以上23歳未満(扶養認定日の属する年の12月31日の年齢で判断)については、年収150万円未満に引き上げられましたが、それ以外は変更はありません。
実際には、「税金の扶養」よりも「社会保険の扶養」を気にして働く方の方が多く、社会保険の扶養の範囲内を気にされる方は今回の変更は余り影響しない年代の方の方が多いように思います。
働き控えの解消を目指すのであれば、今後は19歳以上23歳未満の方以外についても見直しが必要ではないかと考えます。
---
(文責 社会保険労務士 田中 数基)