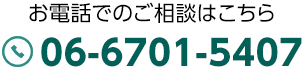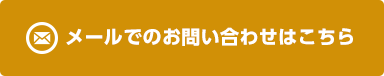2025年1月~12月
人事評価を複数人で行う時の知っておきたいルール その2(2025.5月号)
●人事評価を複数人で行う時の知っておきたいルール その2(2025.5月号)
皆様の会社では人事評価を行っておられるでしょうか?
人事評価とは「会社が社員に要求する職務遂行能力の程度、遂行結果、貢献度、遂行態度などを評価し、人事処遇・賃金処遇・人材育成に反映させる基礎的な手段である(日経連 2002)」と定義することができます。
処遇への反映だけでなく、人材の育成という視点が極めて大事なのですが、このことに関してはまた別に機会に解説したいと思います。今回のメルマガでは如何に人事評価を公正に行うか、ということについて先人が積み上げてきた統一ルールをご紹介したいと思います。
その前に、社長一人が評価者である会社の場合は、このような統一ルールを意識する必要はありません。もっと言えば社長の主観で結構です。社長の価値観や思いを素直に評価に出せばそれで構いません。その主観が法令に抵触するとか、公序良俗に反しない限り、自由に行えばよいのです。社長の価値観がその会社の評価軸であり、その結果に対して全責任を負う訳ですから。
ただ部課長に一次評価をさせる場合など複数人で評価を行う場合は、統一ルールを理解しておく必要があります。そうしないと同じ事実を見ていても、評価者によって著しい違いが生じ、公正さが失われ、部下から不信感を買うことになるからです。
人事評価は諸刃の剣です。やり方を間違うとかえって不信感、不満感が増幅され、やらない方がマシだったということになりかねません。はっきり言いまして、上司と部下との間に最低限の信頼関係がないとか、上司が敬われていないケースではやらない方がマシです。
最低限の信頼関係があるという前提において、評価にエラーを起こさないためにはどのようなことに気を付ければ良いのでしょうか?3月号に引き続き、以下代表的なエラーを解説します。
1.ハロー効果
評価者が被評価者の一部の顕著な特徴(例:外見、性格、特定のスキル)に強く影響され、他の評価項目まで高く(または低く)評価してしまう誤り。対象者の一部の優れた点、劣った点に惑わされ、他の部分についても同様に優れていたり、劣っているように考えてしまうエラー
例:Aさんはプレゼンが非常に上手で、発言も明確なため、評価者はAさんを「仕事全般に優れている」と感じ、実際には成果が平均的な業務についても高評価を与えてしまう。
2.寛大(厳格)化傾向
評価者が全体的に甘く(寛大)または厳しく(厳格)評価してしまう傾向。個人の性格や評価に対する感情が影響しやすい。評価結果が甘・辛のいずれかに偏る傾向。
例:上司のBさんは「部下にはモチベーションを下げてもらいたくない」と思っているため、実際の成果に関わらず、部下全員に高評価を与えてしまう(寛大化)。
逆に、上司のCさんは「自分に厳しく部下に対する期待値が高い」ため、ほとんどの部下に厳しい評価を下してしまう(厳格化)。
3.中心化傾向
目立った評価を避けるため、どの被評価者にも平均的な評価(真ん中の評価、5段階なら3に偏る)を付けてしまう傾向。評価の正確性が失われる。標準ランクが真ん中に偏り、優劣ができない傾向。評価に自信がない場合や、事実をよく見ていないことが原因で、よく出現するエラー。
例:評価表が5段階評価になっているときに、「波風を立てたくない」という理由から、どの部下にも「3」を付け続ける。実際には明らかに優れている人や問題がある人がいても、差をつけない。
4.対比誤差
他の被評価者との比較によって評価が歪む誤り。評価基準が個人間の相対比較になってしまい、公平性が損なわれる。評価者が自分自身や他人を基準において、その比較で評価をつけてしまうエラー。
例:前に評価したDさんが非常に優秀だったため、次に評価されたEさんも本来は良い成果を出しているが、相対的に見劣りしてしまい、過小評価されてしまう。
5.論理誤差
評価項目間に論理的な関連があると誤って解釈し、1つの項目の評価が他の評価項目に不適切に影響を与える。「あれがよければ、これもよいはず」と自分の論理で評価項目を結びつけて判断を誤るエラー。
例:「積極的に発言する社員は、リーダーシップがあるはず」と評価者が思い込み、実際にリーダーシップがあるかどうかを十分に検証せずに高評価をつけてしまう。
6.期末効果
評価期間全体を見ず、直近のパフォーマンスや出来事だけで評価してしまうエラー。最近の印象が強く残るため起きやすい。直近の成果や出来事をより強く評価してしまうエラー。
例:Fさんは年間を通して成果が安定していたが、期末に一度大きなミスをしたため、それだけが印象に残り、全体の評価が大きく下がってしまう。
【これらのエラーを防ぐ対策】
(1)あらかじめ、自分の評価傾向を把握しておく(他人に甘いとか、印象に左右されやすいとか)
(2)日頃から部下をよく観察し、記録をもとに評価する(できれば「部下指導日誌」を付けておくことをお勧めします)
(3)あらかじめ、評価シートなど会社の定めるものをよく読み、 評価ルールに沿った評価をする(自分の解釈を入れず会社の基準で粛々と)
(4)印象や他者との比較ではなく、事実の裏付けを確認して評価を行う
(5)人物(性格、おいたち、年齢)を評価しない(表に出ている行動を中心に)
(6)途中評価(プロセス)で報連相(コミュニケーション)を密にする
(7)手続きの公平性は求められても、結果の平等は求めない
(8)評価者会議を開き認識をそろえる
(9)自分に自信を持つ(管理職として自己研鑽)
(文責 特定社会保険労務士 西村 聡)